2014年の第1回公募以降、小規模事業者の販路開拓・業務効率化を資金面から支援している小規模事業者持続化補助金。個人事業主やフリーランスの方でも申請が可能な補助金であり、補助対象となる経費の多さに魅力を感じ、利用を検討されている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、個人事業主・フリーランスの方に向けて、小規模事業者持続化補助金の概要や申請時のポイントを解説します。記事後半では、合わせて検討したい補助金制度や支援金制度も紹介していますので、ぜひ最後までご一読ください。
※:本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。
本記事でわかること
・個人事業主の方が小規模事業者持続化補助金を利用するための条件
・個人事業主の方が追加で提出する書類
・過去に採択された個人事業主の申請事例
・個人事業主の方が利用する際に注意すべきポイント
・あわせて検討したい支援制度
目次
小規模事業者持続化補助金は個人事業主・フリーランスも利用できる
_記事内画像001-1024x577.png)
小規模事業者持続化補助金の公募要領には、補助対象者の範囲として「個人事業主」と明記されています。
【小規模事業者持続化補助金の補助対象となりうる者】
・会社および会社に準ずる営利法人
・個人事業主
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
ただし、すべての個人事業主が補助対象となるわけではありません。下記に当てはまる場合は、申請・採択対象外となりますのでご注意ください。
【小規模事業者持続化補助金の補助対象外となる個人事業主】
・商工業者以外の個人事業主
・医師、歯科医師、助産師
・収入が系統出荷だけの個人農業者(林業・水産業者)
・申請時点で開業していない者
なお、補助金額の詳細や対象経費など、補助対象者以外の情報を確認したい方は、下記記事もご覧ください。
関連記事:2025年の小規模事業者持続化補助金について解説!対象者や金額、変更点をご紹介
小規模事業者持続化補助金における個人事業主の採択事例10案をご紹介
_記事内画像002-1024x577.png)
続いては、実際に採択された個人事業主の事業計画事例を見ていきましょう。
【個人事業主の採択事例(第16回公募)】
・地域広報活動およびホームページ制作による新規顧客獲得
・高画質ドローン撮影による高画質コンテンツの制作
・英語コーチングスクールのオンライン・オフライン集客施策
・外国人観光客向けの看板設置による多言語対応での販路開拓
・専門性を活かした革小物修理サービスの立ち上げ
・駐車場の整備によるリピーターの拡大と宣伝による新規顧客の獲得
・割烹料理の新メニュー開発による新規顧客獲得
・駅前商店街への新拠点出店
・持続可能な店舗運営を目的とした店内環境改善および人員安定化計画
・イートイン事業、新メニュー展開による新規顧客獲得
以上は全国の採択事例の一部となります。ご自身の業種に近い採択事例を探したい場合は、補助金申請をサポートする専門家への問い合わせがおすすめです。
個人事業主が小規模事業者持続化補助金を活用する際の注意点
_記事内画像003-1024x577.png)
続いては、実際に個人事業主が申請・利用する際に抑えておきたい注意点を3つ紹介します。
企業・法人として申請する際と異なる手続き内容や、新たに設けられた制度の利用方法、申請において最も重要となる「事業計画書」策定のコツなどを解説していますので、申請前にぜひチェックしてみてください。
ポイント①必要となる書類
個人事業主が小規模事業者持続化補助金に申請する際には、「全申請者が必須の提出資料」「申請内容に応じて必要となる提出資料」2種類の書類を用意する必要があります。
「全申請者が必須の提出書類」は、下記8点です。このうち、一部書類は申請システムに直接入力するため、提出・添付の必要はありません。
【個人事業主が必ず提出しなければならない書類】・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1)(※1)
・経営計画書兼補助事業計画①(様式2)(※1)
・補助事業計画書②(様式3)(※1)
・事業支援計画書(様式4)
・補助金交付申請書(様式5)(※1)
・宣誓・同意書(様式6)(※1)
・開業の事実または決算内容がわかる書類の写し
※1:電子申請システムに直接入力します
最後に記載した「開業の事実又は決算内容がわかる書類の写し」は、個人事業主が申請する場合にのみ提出が必要な書類となります。具体的には、下記3点の書類を提出します。
【開業の事実または決算内容がわかる書類の写し(※)】
・直近の確定申告書
→第一表および第二表および収支内訳書(1・2面)
→第一表および第二表および所得税青色申告決算書(1~4面)
・開業届および売上台帳等の写し
※:マイナンバーが提出書類に記載されている場合は番号を黒塗りにして提出
上記3点の書類のうち、開業届は決算期を一度も迎えていない場合のみ提出できます。一度でも決算期を迎えている場合には、所得額に関わらず確定申告書の写しもしくは所得税青色申告決算書を提出しなければなりません。
なお、書面提出時に税務署受付印が無い場合には、税務署が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)の写し」を追加で提出します。また電子申告している場合には「受付結果(受信通知)」を印刷したものが受付印の代用となりますので、忘れずに添付しましょう。
ポイント②インボイス特例の利用方法
_記事内画像004-1024x577.png)
2025年・令和7年度の小規模事業者持続化補助金では、「インボイス特例」「賃金引上げ特例」が設けられました。ここでは、それぞれの特例の利用方法をご紹介します。
インボイス特例
インボイス特例の対象者は「免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者」となっており、特例が適用された場合補助上限額が一律50万円上乗せされます。利用する場合には、下記追加要件を満たすとともに追加で書類を提出する必要があります。
【インボイス特例の適用追加要件】
・2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者であった事業者
・2023年10月1日以降に創業した事業者で、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者
【必要な手続き・提出書類】
・「インボイス特例の申請に係る宣誓・同意書(様式9)」を確認し、該当箇所にチェックをする
・適格請求書発行事業者の登録が完了していることが分かる書類を提出する
→「適格請求書発行事業者の登録通知書の写し」または「登録申請データの「受信通知」画面の写し」
※:補助対象事業が終了した時点でも要件を満たしている必要があります。
なお、申請時、まだ登録申請をしていない事業者は申請時の時点では書類aおよびbの提出は不要です。ただし、事業が終了し実績報告書を提出する際には上記書類を提出する必要があります。
スムーズに実績報告をするためにも、申請の準備と合わせて登録手続きを進めるとよいでしょう。
賃金引上げ特例
賃金引上げ特例は、最低賃金の見直しが進む昨今の社会情勢をふまえ、積極的な賃上げに取り組む事業者を支援する特例です。
前回公募である2024年度・第16回公募に設けられていた「賃金引上げ枠」が撤廃され、新たに一般型・通常枠で活用できる特例として設けられました。特例を利用することで、補助上限金額を最大100万円引き上げることができます。
2025年度・第17回公募の追加要件および提出書類は下記の通りです。
【賃金引上げ特例の適用追加要件】
・申請事業の終了時点において、事業場内最低賃金(※)が申請時の事業内最低賃金より+50円以上であること
※:直近1か月の支給賃金を参照します。6月に申請した場合は、5月の支払賃金が参照できる賃金台帳を提出してください。また、申請時点および申請事業終了時点において、支給している事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上である必要があります。
【必要な手続き・提出書類】
・申請情報入力画面で特例を選択し、賃金引上げ特例(様式7)画面で「事業場内最低賃金算出表」を入力する
・「賃金引上げ特例・賃上げ加点の申請に係る誓約・同意書」(様式7)を確認し、該当箇所にチェックをする
・申請時に下記2点の書類を提出する
→労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し
→雇用条件が記載された書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書など)
・実績報告書の提出時に下記2点の書類を提出する
→申請事業終了時点における直近1か月分の労働基準法に基づく直近1か月分の賃金台帳の写し
→賃金引上げ後の雇用条件が記載された書類の写し(雇用契約書、労働条件通知書など)
なお、特例の詳細については下記の記事でも詳しく解説しています。利用を検討する際はぜひこちらもご覧ください。
関連記事:2025年の小規模事業者持続化補助金について解説!対象者や金額、変更点をご紹介
ポイント③事業計画書の策定
提出書類のひとつである経営計画書兼補助事業計画、補助事業計画は、申請者が補助金を用いてどのような販路開拓をおこなうかを事務局に説明するための書類です。
制度を利用するには事務局による審査を通過し採択される必要がありますが、これら2点の書類は審査における最重要書類とも言えます。
ほかの補助金制度と異なり、小規模事業者持続化補助金では事業計画書の様式が定められており、所定の記入欄に事業計画を記入しなければなりません。記入スペースが限られているため、計画の要所・伝えるべき要素を簡潔に記載する必要があります。
事業計画書の策定に悩んでいる方は、まずは事務局公式ウェブサイトにて公開されている記入例を参考にしてみると良いでしょう。
また、申請者をサポートする業者を活用することで、質の高い事業計画を効率的に作成できます。普段の業務が忙しい方は、補助金制度への理解が深い中小企業診断士や行政書士などへの相談を検討してはいかがでしょうか。
小規模事業者持続化補助金とあわせて検討したい個人事業主向け支援制度
_記事内画像005-1024x577.png)
ここからは、個人事業主・フリーランスが利用できる補助金・支援金制度の一部をご紹介します。小規模事業者持続化補助金とともに他制度の利用を検討している方は、ぜひご一読ください。
中小企業新事業進出補助金
まずご紹介するのが、新たな事業分野への進出を目指す中小企業等を支援する「中小企業新事業進出補助金」です。
2024年度まで実施されていた「事業再構築補助金」の後継補助金と評価されている通り、幅広い経費が補助対象となっています。
【中小企業新事業進出補助金の活用事例】
・機械加工業でのノウハウを活かした半導体製造装置部品の製造に挑戦
・医療機器製造の技術を活用した蒸留所の建設およびウイスキー製造業への進出
中小企業新事業進出補助金のメリットとしては、補助上限金額が2,500万円~7,000万円と比較的高額である点が挙げられます。新たなビジネスに挑戦する予定がある方は、ぜひ下記記事にて制度の詳細を確認してみてください。
2025年(令和7年)の補助金・助成金をまとめて解説!新制度や活用事例もご紹介
ものづくり補助金:製品・サービス高付加価値化枠
続いて紹介するのは、個人事業主や中小企業の新製品・新サービス開発を支援する「ものづくり補助金」です。
個人事業主・フリーランスの方も申請可能となっているほか、補助上限金額が2,500万円となっているため、機械装置や新システムの導入を検討している個人事業主でも申請しやすい補助金となっています。
【製品・サービス高付加価値化枠の活用事例】
・最新複合加工機による精密加工技術を導入し、高付加価値な製品を開発する
2025年度・第19次締切は4月11日(金)より申請が開始されます。申請方法や必要な準備を確認したい方は、下記記事をあわせてご覧ください。
ものづくり補助金とは?2025年の申請方法や対象事業、金額などを解説
自治体や各省庁による補助金・助成金
一部都道府県や市区町村では、個人事業主や中小企業の競争力強化・事業継続支援を目的とした補助金・助成金制度を設けています。たとえば、新宿区では経営力強化を目指す個人事業主を対象とした「経営力強化支援事業補助金」が2025年1月末まで実施されていました。
また、経済産業省、農林水産省、中小企業庁などの省庁では、上記で紹介した補助金制度とは別に、特定業種を支援する助成金制度を用意しています。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主の方でも申請が可能な補助金制度です。ただし、申請時には直近の確定申告書をはじめとした必要書類と、販路開拓による効率化を目的とした事業計画書を提出しなければなりません。
採択を受け補助金を利用するには、的確な事業状況の分析と持続的発展の見込める事業プラン、そして実現性の高い販路開拓計画の策定が必要です。
初めての申請で書類作成や手続きに不安がある方は、補助金の窓口が申請・手続きをサポートいたします。無料のLINE相談では、補助金申請のサポート実績を持つ中小企業診断士とともに対応いたします。ぜひお気軽にご利用ください。

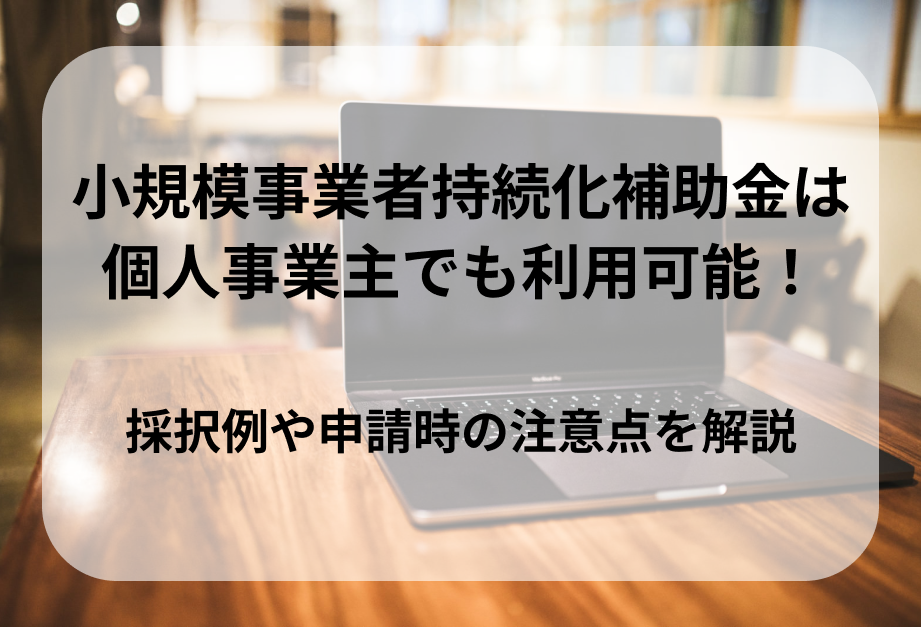
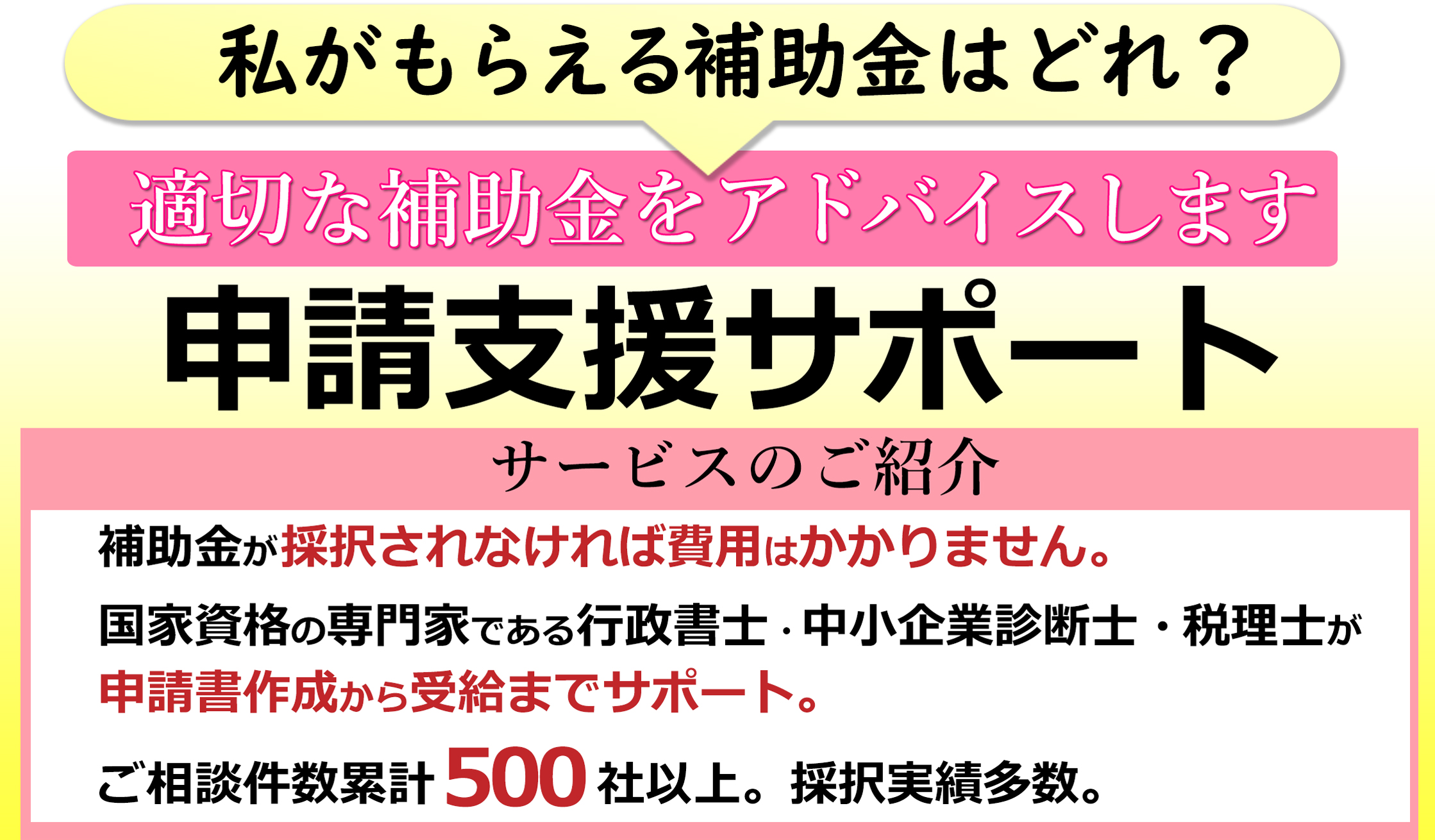

_サムネイル-1-160x160.png)