小規模事業者持続化補助金には「通常枠」と「特別枠」があり、補助率や補助上限額が異なります。小規模事業者持続化補助金を申請する際は、各枠の補助内容の違いを踏まえた上で申請枠を決定することが大切です。本記事では、特別枠の中の「賃金引上げ枠」について概要や利用のメリットを解説します。

【この記事の監修者】
ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史
以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。
【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
小規模事業者持続化補助金は、創業して間もない企業・個人事業主をはじめとして小規模事業者の飛躍に役立つ支援制度のひとつです。なかでも「特別枠」は上手に使うことで大きく効果を上げるチャンスにつながります。記事内の解説を確認して活用を検討してみましょう。
目次
1.小規模事業者持続化補助金とは?
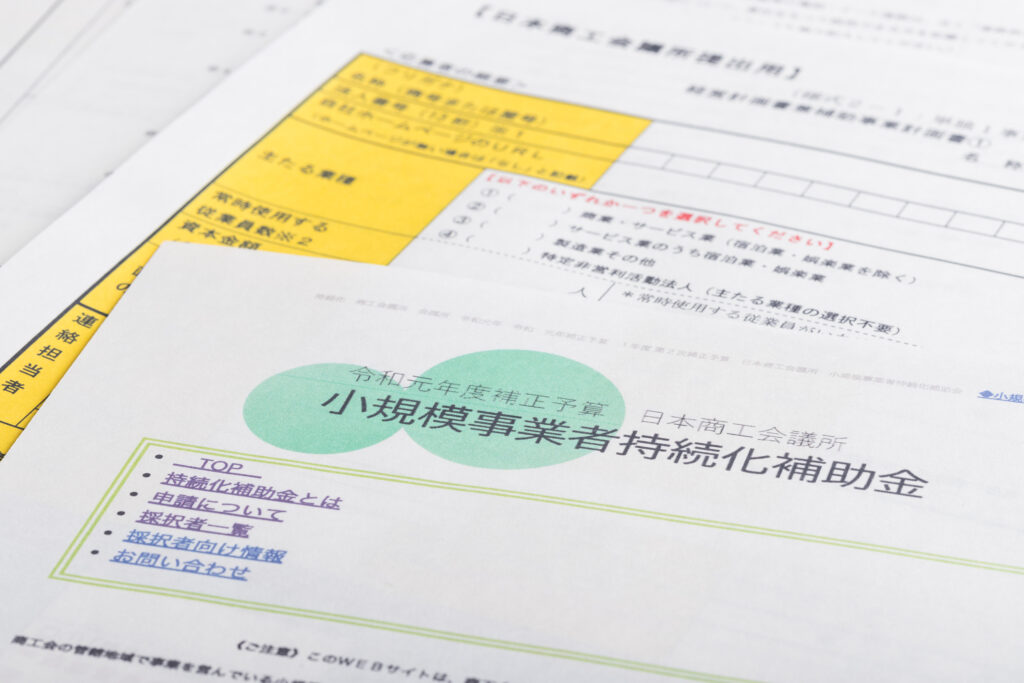
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が販路拡大のために要した費用の一部を補助する制度です。
小規模事業者は、今後数年にわたって「働き方改革」や「被用者保険の適用拡大」、「賃上げ」、「インボイス制度の導入」などさまざまな制度変更に取り組む必要があります。その中で事業の在り方が変わったり、新たな経営課題が発生したりする可能性もあるでしょう。
小規模事業者持続化補助金とは、こうした小規模事業者が抱える課題を支援することを大きな目的としています。
2.賃金引上げ枠の概要
小規模事業者持続化補助金には、「通常枠」や「賃金引上げ枠」、「卒業枠」など5種類の枠があり、それぞれ補助率や補助上限額が異なります。ここでは、賃金引き上げ枠の概要について確認していきましょう。
2-1.要件
物価上昇や働き手不足の影響を受けて、企業でも賃上げを実施するところが増えています。賃金引上げ枠は、積極的に賃上げを行う事業者を支援するための申請枠です。
| 賃金引上げ枠 | |
| 補助率 | 3分の2(赤字事業者は4分の3) |
| 補助上限額 | 200万円 |
| インボイス特例 | 50万円 |
賃金引上げ枠の申請要件は、「事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること」です。たとえば、事業所を置く地域の最低賃金が時給1,000円の場合、1,030円以上に引き上げることで補助金の交付対象となります。
また、賃金引上げ枠に申請する事業者のうち、業績が赤字の事業者については補助上限引き上げに加えて、補助率が3分の2から4分の3へと引き上げられます。
2-2.補助対象経費

小規模事業者持続化補助金の補助対象となるのは、次の経費についてです。
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
⑤旅費
⑥開発費
⑦資料購入費
⑧雑役務費
⑨借料
⑩設備処分費
⑪委託・外注費
たとえば、「機械装置等費」では販路拡大のために購入した機械などの導入費用が対象となります。「家族連れの集客力向上のために購入したベビーチェア」や「生産量拡大のために購入した大型冷蔵庫」など、幅広いものが対象となりますので、ぜひ自社事業で活用できないか検討してみましょう。
ただし、パソコンやタブレット端末、プリンターなどは汎用性が高く、販路拡大以外の目的にも使用できることから本補助金では対象外とされています。
3.賃金引上げ枠のメリット
小規模事業者持続化補助金を賃金引上げ枠で申請することには、主に2つのメリットがあります。それぞれくわしく解説していきましょう。
3-1.補助上限額の増額
賃金引上げ枠は、通常枠に比べて補助上限額が増額されています。通常枠では補助上限額が50万円であるのに対し、賃金引上げ枠では最大200万円の補助金が受けられます。
補助金が最大4倍まで増額されるため、「販路拡大のために大がかりなリフォームを考えている」、「新商品の構想があるが、開発費が工面できずなかなか実行に移せない」という場合は、ぜひ賃金引上げ枠での申請を検討してみましょう。
なお、通常枠と賃金引上げ枠を併用することはできず、どちらか一方の枠で申請する必要があります。
3-2.赤字業者は補助率アップ&優先採択の対象

賃金引上げ枠では、前述の通り赤字業者に対して補助率が3分の2から4分の3へ引き上げられます。たとえば、販路拡大にかかった費用が150万円の場合、通常は100万円が補助上限となりますが、赤字業者の場合は112万5,000円まで補助金を受けることが可能です。
「資金繰りが厳しくなかなか販路拡大に取り組めない」という場合は、賃上げ引上げ枠を活用することを検討してみましょう。
また、赤字業者は「政策加点」の「赤字賃上げ加点」として加点対象となり、優先採択が受けられることも大きなメリットです。
4.小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)の申請ステップ
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠は、次のステップに沿って申請手続きを行います。
①申請要件の確認
②申請書類の作成
③商工会議所から事業支援計画書の交付
④補助金の申請
それぞれくわしく確認していきましょう。
4-1.申請要件の確認
まずは、賃金引上げ枠で申請ができるか確認を行います。
賃金引上げ枠の申請要件は、「事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること」です。もしすでにこの基準をクリアしている場合は、「直近1ヶ月で支給している賃金+30円以上」の賃上げを行う必要があります。
なお、雇用している従業員がいない場合は、賃金引上げ枠の対象外となり、補助金を受けることができません。
4-2.申請書類の作成
次に、申請書類の準備・作成を行います。申請に必要となる書類が次の通りです。
・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書
・経営計画書兼補助事業計画書
・補助事業計画書
・事業支援計画書
・補助金交付申請書
・宣誓・同意書
・賃金引上げ枠の申請に係る誓約書
・労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分)
・役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類
また、法人については「貸借対照表および損益計算書」や「株主名簿」、個人の場合は「確定申告書」もしくは「所得税青色申告決算書」なども必要となります。提出書類や作成書類が多いため、申請時は計画的に手続きを進めましょう。
4-3.商工会議所から事業支援計画書の交付
上記必要書類のうち、事業支援計画書については地域の商工会・商工会議所が発行します。事業支援計画書発行の受付は、原則公募締切の1週間前までとなっていますので、余裕を持って発行手続きを行うようにしてください。
また、事業支援計画書の発行にあたって「経営計画書」および「補助事業計画書」の写しが必要となるため、この2点については先んじて作成しておきましょう。
4-4.補助金の申請
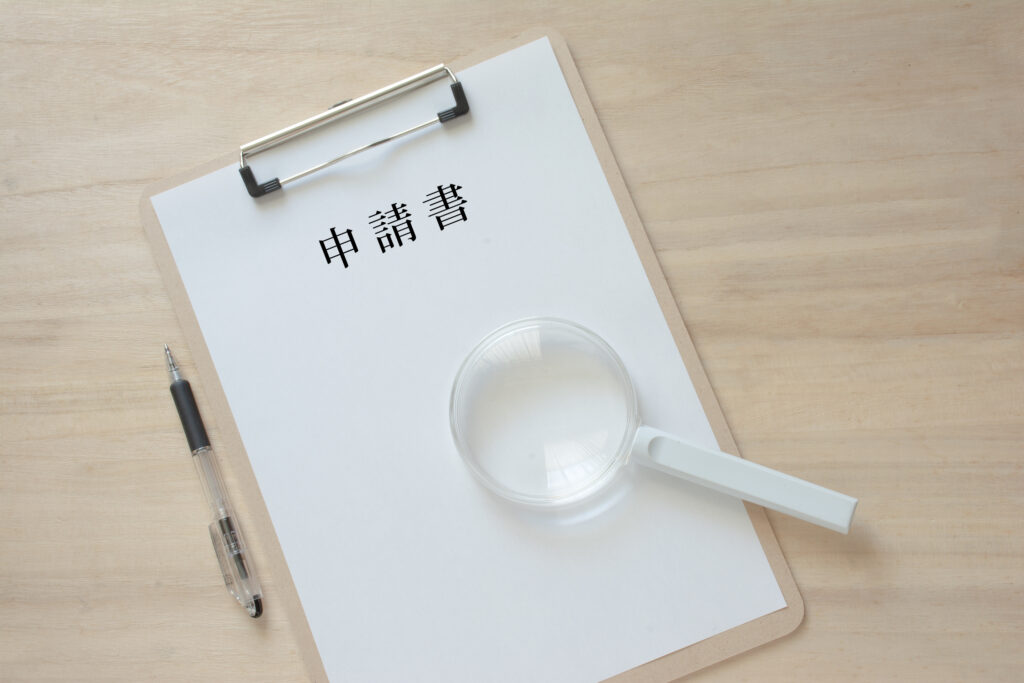
提出書類が揃ったら、電子申請または郵送にて申請手続きを行います。商工会・商工会議所地区によって申請先が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、電子申請では補助金申請システム(Jグランツ)を利用しますが、Jグランツでの申請にあたって「gBizID」が必要となります。gBizIDの登録・発行には数週間ほど時間がかかりますので、前もって発行手続きを行っておきましょう。
なお、個人事業主はマイナンバーカードを使ったオンライン申請でgBizIDの即時発行が可能です。詳しい方法は下記記事をご確認ください。
なお、個人事業主はマイナンバーカードを使ったオンライン申請でgBizIDの即時発行が可能です。詳しい方法は下記記事をご確認ください。関連記事:GビズIDプライムはオンライン手続きが可能!申請方法や2段階認証の手順を解説
その後、提出した書類に基づいて審査が行われ、採択の可否が判断されます。
5.小規模事業者持続化補助金(賃金引上げ枠)の注意点
小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠を利用する際は、次の3点に注意が必要です。
・賃上げをしていない場合、補助金は出ない
・補助金は実績報告書の後に支払われる
・各種申請のスケジュールを確認する
それぞれくわしく確認していきましょう。
5-1.賃上げをしていない場合、補助金は出ない
賃金引上げ枠では賃上げを行う事業者が対象となっているため、当然ながら賃上げに取り組んでいない事業者は補助金の対象外となります。
「事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること」、もしくは「直近1ヶ月で支給している賃金+30円以上の賃上げを行う」の要件を満たさない場合は、交付決定後であっても補助金の交付が行われません。
賃金引上げ枠で申請を行う際は、どのように賃上げに取り組むかしっかりと計画を立てておきましょう。
【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
補助金を受給するためにも、従業員の最低賃金の算出方法について自身で公式資料をよく確認するか、専門家に相談しましょう。
5-2.補助金は実績報告書の後に交付される
小規模事業者持続化補助金を申請する際は、補助金交付のタイミングにも注意が必要です。
補助金が交付されるのは、採択が決定した後に補助事業を実施し、実績報告書を提出した後となります。
補助事業にかかる費用は、一旦事業者で全額支払う必要があるため、その間の資金繰りに問題が生じないかよく考慮しておきましょう。
5-3.各種申請のスケジュールを確認する

小規模事業者持続化補助金では、採択が決定された後に「実績報告書」と「「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の提出を行います。これら2つの報告書にはそれぞれ提出期限が定められていますので、よくスケジュールを確認しておきましょう。
| 提出書類 | 提出期限 |
| 実績報告書 | 補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日 |
| 事業効果および賃金引上げ等状況報告 | 事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内 |
6.まとめ
小規模事業者持続化補助金は、販路拡大に取り組む小規模事業者を支援するための制度です。中でも賃金引上げ枠は、通常枠に比べて補助上限額も大きくなるため、ぜひ活用を検討したい補助金です。
小規模事業者持続化補助金は新たな機械の導入やチラシの制作、店舗のリフォームなど幅広いビジネスシーンで利用できますので、自社事業で活用できるところはないか検討してみましょう。



