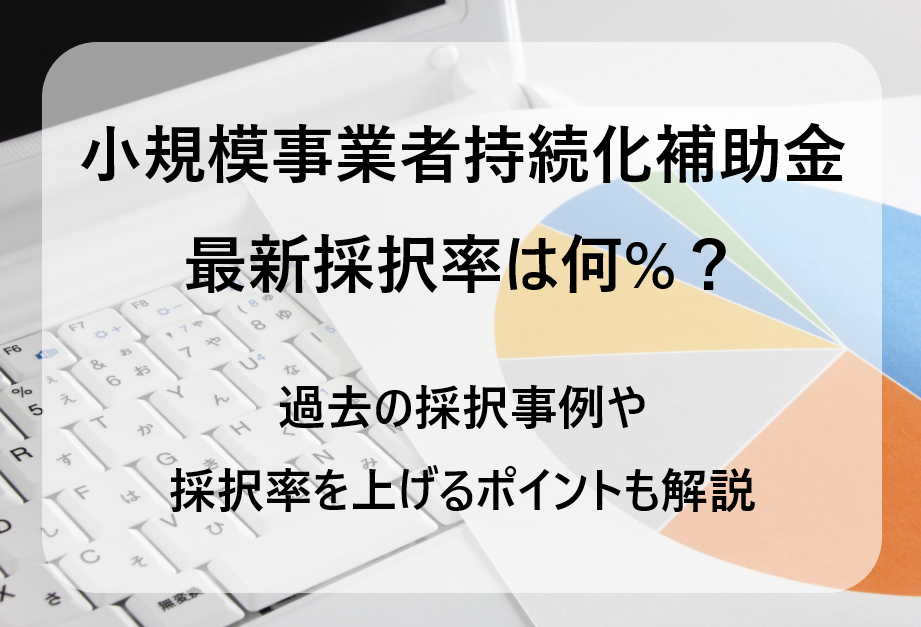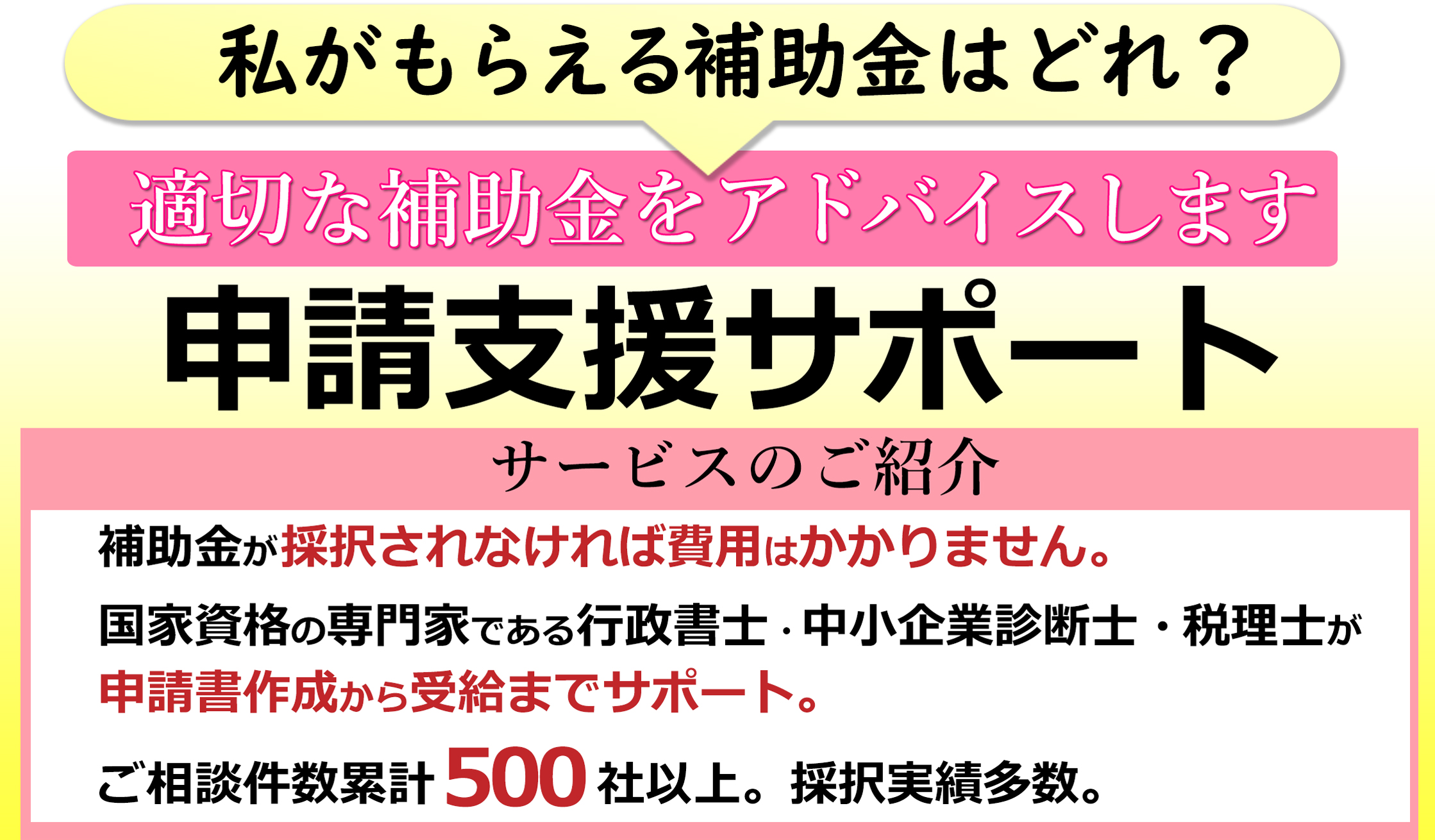小規模事業者持続化補助金を運営する補助金事務局では、毎回の「採択率」を公表しています。本記事では、最新の採択率をご紹介しつつ、採択事業の一例や採択率を上げるためのポイントを解説します。
申請前に制度を理解し採択率を少しでも上げたい方はぜひ本記事をご一読ください。
※本記事は、執筆時点の情報をまとめたものです。最新情報と異なる可能性があるため、各種補助金制度の詳しい情報については公式サイトも併せてご確認ください。

【この記事の監修者】
ライズ法務事務所 行政書士 米山浩史
以前は霞が関(中央官庁)で国家公務員として補助金行政、許認可業務、政策の企画立案等に従事。また、各省庁から複数名ずつ派遣されて創設された省庁横断チームに参画して新しい支援制度の設立も担当した。業務で培った広い視野と制度知識をもとに、企業・事業者の補助金申請をサポートしている。
【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
小規模事業者持続化補助金は、個人事業主や小規模事業者の販路開拓等に役立つ支援制度のひとつです。
しかし、申請すれば誰でも受給できるという制度ではなく、受給するためには審査を受けて採択される必要があります。採択確率を高めるため、記事内の解説を確認しつつ事前準備を進めましょう。
本記事でわかること
・最新公募の採択率
・過去の採択率
・業種別の最新採択事例
・採択率を上げるポイント
目次
小規模事業者持続化補助金の第14回採択率は62.5%
第14回公募では、全国から13,597件の申請があり、8,497件が採択されています。採択率は62.5%でした。
なお、小規模事業者持続化補助金は商工会・商工会議所で申請を受け付けています。採択結果の詳細についてもそれぞれのサイトにまとめられていますので、詳細は下記のリンクよりご確認ください。
小規模事業者持続化補助金の採択率推移
続いては、過去の採択率について見ていきましょう。2014年にスタートした小規模事業者持続化補助金は、これまでに15回の公募が行われてきました。そのうち、第14回までの公募結果が公表されています。
| 小規模事業者持続化補助金(一般枠)過去の採択率 | |||
| 公募 | 応募数 | 採択件数 | 採択率 |
| 第14回 | 13,597件 | 8,497件 | 62.5% |
| 第13回 | 15,308件 | 8,729件 | 57.0% |
| 第12回 | 13,373件 | 7,438件 | 55.6% |
| 第11回 | 11,030件 | 6,498件 | 58.9% |
| 第10回 | 9,844件 | 6,248件 | 63.4% |
| 第9回 | 11,467件 | 7,344件 | 62.9% |
| 第8回 | 11,279件 | 7,098件 | 69.7% |
| 第7回 | 9,339件 | 6,517件 | 69.0% |
| 第6回 | 9,914件 | 6,846件 | 53.9% |
| 第5回 | 12,738件 | 6,869件 | 44.2% |
| 第4回 | 16,126件 | 7,128件 | 51.6% |
| 第3回 | 13,642件 | 7,040件 | 65.1% |
| 第2回 | 19,154件 | 12,478件 | 65.1% |
| 第1回 | 8,044件 | 7,308件 | 90.8% |
第1回公募では9割を超える採択率で多くの事業者が補助対象となりましたが、近年の公募では6割前後となっています。
また、小規模事業者持続化補助金は、事業者を取り巻く社会情勢の変化に合わせて制度内容を変えつつ公募をおこなってきました。
例えば、2020年には新型コロナウイルスの流行阻止と事業継続を目的とした感染対策に取り組む事業者を対象とした「コロナ特別対応型」が新設されました。さらに、2021年にはアフターコロナ時代を見据えた取り組みを支援する「低感染リスク型ビジネス枠」が設けられています。
上記2つの特別支援枠の採択率は下記の通りです。
| 小規模事業者持続化補助金「コロナ特別対応型」の採択率 | |||
| 公募 | 応募数 | 採択件数 | 採択率 |
| 第5回 | 43,243件 | 16,498件 | 38.1% |
| 第4回 | 52,529件 | 15,421件 | 29.3% |
| 第3回 | 37,302件 | 12,664件 | 33.9% |
| 第2回 | 24,380件 | 19,833件 | 81.3% |
| 第1回 | 6,744件 | 5,503件 | 81.5% |
| 小規模事業者持続化補助金「低感染リスク型ビジネス枠」の採択率 | |||
| 公募 | 応募数 | 採択件数 | 採択率 |
| 第6回 | 11,721件 | 8,040件 | 68.5% |
| 第5回 | 6,208件 | 4,138件 | 66.6% |
| 第4回 | 8,243件 | 5,780件 | 70.1% |
| 第3回 | 8,056件 | 5,022件 | 62.3% |
| 第2回 | 10,205件 | 5,361件 | 52.5% |
| 第1回 | 7,827件 | 3,512件 | 44.8% |
採択事例を業種別に紹介

ここまでは小規模事業者持続化補助金の採択率を見てきましたが、採択されるためのヒントとして、どのような事例が実際に採択されているかも確認してみましょう。
本記事では、結果が公表されている公募から、申請業者数が多い傾向にある飲食業・製造業・サービス業の採択事例をまとめました。
【飲食業】
・新設備の導入によるメニュー開発・広報活動の活性化を通した幅広い世代への販路拡大
・店舗オリジナル商品の冷凍販売による販路開拓
・地元のフルーツを活用した新商品開発
【製造業】
・新規設備導入による新市場への参入と作業効率の向上
・産業用ドローンを導入し新規サービスを開発
・若年層をターゲットにデザイン性を重視したリノベーション事業を展開
【サービス業】
・新規顧客獲得と地域のコミュニティ活性化を目的としたワークショップ事業
・ホームページのリニューアルおよび自社パンフレット作成による新規顧客の開拓
・海外商談会へ出展および英文ホームページ作成による販路開拓
幅広い費用が補助費用となっている小規模事業者持続化補助金では、補助範囲を生かした販路開拓・新事業展開計画が採択されています。
どのような費用が補助対象となっているかを詳しく確認したい方は、制度概要を解説している下記記事もご確認ください。
2024年の小規模事業者持続化補助金について解説!対象者や金額、変更点をご紹介
採択率を上げるために意識すべきポイント
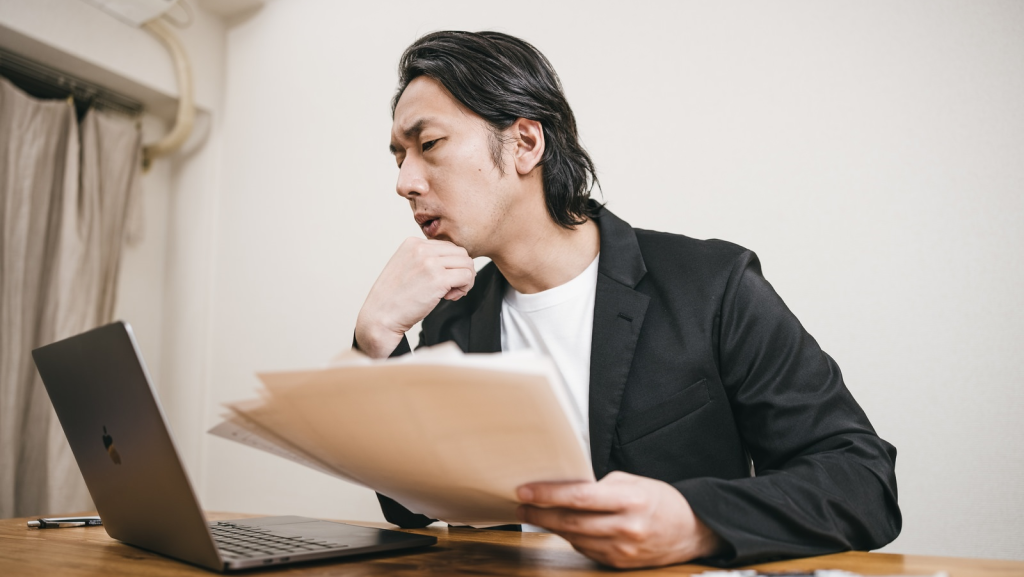
小規模事業者持続化補助金は有識者による審査が行われており、特定の要素を入れることで必ず採択される……といった「必勝法」は存在しません。
その一方で、「採択率を上げるためのポイント」は存在します。ここからは、申請を予定されている方に向けて意識すべき3つのポイントを解説していきます。
審査項目を把握する
小規模事業者持続化補助金のガイドブックには「どのような項目が審査されるか」が記載されています。審査項目の把握は、採択率向上における最も重要なポイントです。
ガイドブックに掲載されている「審査のポイント」に基づく採択のポイントは下記の通りです。
【採択のためのポイント】
・自社の経営状況、製品・サービス、強みを適切に把握する
・自社の強み、対象市場の特性をふまえて経営方針や目標、今後のプランを立てる
・具体的かつ申請する事業者にとって実現可能性が高い事業計画を策定する
・今後の経営方針・目標を達成するために必要かつ有効な事業計画を策定する
・小規模事業者ならではの創意工夫の特徴がある事業計画を策定する
・ITを有効に活用する取り組みを盛り込んだ事業計画を策定する
・事業実施に必要な費用を盛り込んだ事業計画を策定する
・事業費は計上・積算を正確・明確に行い、真に必要な金額を計上する
申請時には、上記ポイントを抑えつつ準備・資料作成を進めましょう。
加点項目を満たす
小規模事業者持続化補助金の採択審査では、一定条件を満たす事業者を対象とした加点制度が設けられています。記事執筆時点の最新公募では「重点政策加点」と「政策加点」の2通りが存在します。
【行政書士 米山浩史氏からのコメント】
加点は、「重点政策加点」と「政策加点」からそれぞれ1種類、合計2種類までとなっています。それ以上選択してしまうと加点審査の対象とならなくなってしまう点に注意が必要です。
【重点政策加点】
1.赤字賃上げ加点
賃金引上げ枠申請事者のうち、赤字である事業者を対象とした加点。
2.事業環境変化加点
ウクライナ情勢や原油価格、LPガス価格などの高騰による影響を受けている事業者を対象とした加点。
3.東日本大震災加点
福島第一原子力発電所の影響を受け、避難指示等の対象となった地域の事業者および被害を受けた水産加工業者等を対象とした加点。
4.くるみん・えるぼし加点
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく「くるみん認定」を受けている事業者、もしくは女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく「えるぼし認定」を受けている事業者を対象とした加点。
【政策加点】
1.賃上げ加点
最低賃金の引き上げに加え更なる賃上げを行い、従業員へ成長果実を分配する意欲的な事業者を対象とした加点。
2-A.パワーアップ型加点(地域資源型)
地域資源等を活用し、良いモノ・サービスを高く提供して付加価値向上を図る目的で地域外販売・新規事業立ち上げを行う事業計画を対象とした加点。
2-B. パワーアップ型加点(地域コミュニティ型)
地域の課題解決・暮らしの実需に応えるサービスを提供する小規模事業者が、地域内の需要喚起を目的とした取り組みを行う場合を対象とした加点。
3.経営力向上計画加点
各受付締切日の基準日までに、「経営力向上計画」の認定を受けている事業者を対象とした加点。
4.事業承継加点
各受付締切日の基準日時点で代表者年齢が満60歳以上で、かつ後継者候補が中心となって事業を進める事業者を対象とした加点。
5.過疎地域加点
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める過疎地域に所在し、地域経済の持続的発展につながる取り組みを行う事業者を対象とした加点。
6.一般事業主行動計画策定加点
従業員100人以下の事業者で、「女性の活躍推進企業データベース」に女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者、もしくは従業員100人以下の事業者で「両立支援のひろば」に次世代法に基づく一般事業主行動計画を公表している事業者を対象とした加点。
これらの加点項目は、経営計画書(様式2)や補助事業計画②(様式3)といった申請書類にあるチェック欄への記入で申請が可能です(※)。
※:一部加点項目については、追加記入項目および追加提出書類が存在します。詳しくは、公募要領の該当箇所を確認するか、申請をサポートする中小企業診断士、行政書士などにお問い合わせください。
制度目的に沿った事業計画書を不備なく作成する
前述の通り、小規模事業者持続化補助金は申請する事業計画を「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)にまとめて提出します。
記入する用紙が指定されているため、必須項目の記入漏れが避けられるというメリットがありますが、一方で記入欄が制限されているという点には注意が必要です。また、経費明細表や資金調達方法欄など、指定された欄に不備なく金額を入力しなければなりません。
各種金額を記入する際には、資料を手元に用意しダブルチェックができるようにしておきましょう。また事業計画書には、制度の目的である「販路開拓とそれに伴う業務効率化による生産性向上・持続的発展」を明示することが大切です。
まとめ
小規模事業者持続化補助金は、近年は6割前後の割合で採択される傾向にあります。
申請すれば誰もが採択されるというものではなく、補助金を利用するには制度内容を理解したうえで具体的な販路開拓プランを記載した事業計画書を作成する必要があります。
事業計画書の作成を不備なく効率的に行いたい方は、申請をサポートする専門家への相談を検討してはいかがでしょうか。士業事務所である補助金の窓口では、補助金申請サポート実績を持つ中小企業診断士が申請・書類作成を補助します。
無料のLINE電話相談にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談ください。